人生はサーカス
人生はサーカス
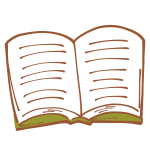
「人生はサーカス」とは、私が十代の頃に読んだ「本」の題名である。
他にも同名の書籍がいくつか出ている様だが、多分それらではない。はたし
てそれが本当にその本の題名であったのかどうかも、正直あやしい。もう、
数十年も前のはなしだ。私はなぜかその言葉に妙に魅かれた。その本の肝心
の中身はと言えば・・実は、おぼろげな記憶しかない。何か「不可思議な
話」や「奇妙な話」を寄せ集めた、翻訳された短編集のような記憶がある。
その何れかが、心に残っている・・というたぐいのことでもない。
「題名」、その本の「題名」だけが、記憶から離れないのだ。小学校の頃、
図書館から無造作に借りてきた、何冊かの内の一冊だったのだろう・・・
2月19日
本堂のやや北側に位置する、小さな宗務室のテーブルを挟んで、私と紅風は
座った。紅風とは、私が幼い頃に同居していた叔母である。叔母といっても
それ程、年が離れてないせいか、「姉」だと思っていた。今もそれは変わっ
ていない。「紅風」とは彼女の書道においての雅号である。
まず、お互いの好物であるコーヒーをいれた。我々は一日に実に多くのコー
ヒーを飲む。熱い湯気の出るカップを手に取り、口をつけた。
まだ温もり切らない、肌寒い室内で飲むコーヒーの最初の一口のなんと美味
しいことか・・・。私はおもむろに、「書」と「ノート」を手にした。
私は紅風の「書」には心魅かれる。「書」は読むものではなく、みるもので
あるという。みる・・「見る」「観る」だろうか、いづれにしても「文字」
を通して、「文字」の奥にある世界に触れるということなのだろう。
「書」にかぎらず、すべての芸術の世界は、そうしたものなのだろうか。
眼に見えない世界を、眼に見える世界にと表わす・・そうしたものなのだろ
う。昔、真宗の僧侶の書かれたものの中に「絵画で言えば、自然の光景を画
いたとき、青い色というだけでなくー青さーというものが感じられなけれな
らない、その(さ)という世界が、眼に見える世界の奥にある世界ではな
いでしょうか。」と記されていた記憶がある。確かにその通りだな。
それは、この世に現れたる、あの世(まぁ、真実界でもいいが)からの働き
かけなのだろう・・・。
さて、その日は紅風との親睦の日である。かねてより、彼女の嫁ぎ先である
津山へ私が出向いたり、また夫の所用に便乗して、彼女が岡山へ来たりして
近況などを報告し合ったりしている。平成28年4月に熊本・大分を中心に
九州では、大きな地震があった。九州には我々の親族もいる。そして、
鹿児島・宮崎は、大正10年の春に、紅風の父(私の祖父)の一族が都城
から岡山へ転住するまでの数百年間、居住した土地であり、われわれにとっ
ても、それは重要な意味を持つ心の礎といってもいいかもしれないのだ。
私と紅風は、その頃から、「鹿児島から始まる信心の息吹」に触れることに
した。それは我々にとっても、身の引き締まる様なものであった。「信仰」
とは「信心」とは、それを受け入れ、保ち続けるということが、いかに命が
けのことなのかが、よく・・理解出来たのだった。
その日は、紅風が私に彼女の書いた「書」の下書きを見せるということと、
我々にも縁深い、安芸の念仏者「月岡 松風」についての、彼女が知る限り
で「思い深き言葉」・・在家の念仏者であった「月岡」のその念仏生活より
生まれた「仏徳讃嘆の言葉」をなぞろうということであった・・・。それ
は、紅風にとっても、私にとっても、それぞれの若き時代の苦悶、煩悶の心
に、力強き念願の炎を、暗闇の中には真の「光と温もり」をあたえてくれる
が如きものであったのだ・・言葉・・言葉である。
「月岡」は昭和24年に亡くなっている。
瞬く間に・・時は過ぎた。
私たちは、もう、三杯目のコーヒーを飲もうとしていた。途中、父から御津
にいる友人に会いそのまま自宅に帰るとの連絡が入った。紅風の夫が迎えに
くるまでには、まだ時間がある。再び、コーヒーを飲み始めていた・・・。
令和2年4月

年号が「令和」に改まってからはや一年が経とうとしている。
また、春はきた、昨年と同様に。同じ場所に桜はその薄紅色の柔らかなる姿
を気取ることなく、咲き誇っている。その少し前から咲き始めた鮮やかな
ピンク色の桃の花もいまだ健在である。その他・・様々な花々が・・赤磐の
春は美しい・・・
その日私は久々に紅風と会った。夫の岡山での用事の終わる待ち時間、私に
連絡してきた。私は岡山に戻り、私たちは「喫茶K館」に入った。「K館」は
広々とした店内で、くつろげる雰囲気の店である。私は好きだ。
こうした時には、ふいに、我々は祖母の話になる。私の祖母、そして、
紅風の母だ。この祖母に関する「印象」はまったくといっていいほど、重な
りあっているのだ。「気は強かった」だの「勝気であった」だの「一途で
あった」だの・・まぁ、そうした印象であった。そして、たいてい同じ様な
場面が記憶に残っているようであった。私を含め、孫たちは皆祖母は死なな
いと思っていた。それ程生命力に溢れた人物であった。しかし、平成23年
8月に祖母は亡くなった。享年101才であった。最晩年は津山の施設に
入っていた。最後まで祖母に付き添っていたのは紅風であった。祖母も嬉し
かったであろう。紅風にとっても、出来る限りの事が出来た母親に対しては
何ら後悔は見いだせないのだ。
この祖母・・美代子なのだが、彼女は広島県尾道市で生まれた。そして祖父
と一緒になるまでの間、尾道で育った。尾道のことを愛していた。亡くな
る直前まで尾道のことを言っていたという。祖母にとって尾道は離れがたき
心の古里でもあったのだ。私の母も紅風も、そして私も、子どもの頃から尾
道にはよく行った。この町は懐かしい思いでの宝庫でもある。
この町での思い出を話す時の祖母の眼は輝いていた。そして、芙美子さんは
私より七才年上で・・とか、芙美子さんの時代はまだ袴の時代で、とかよく
言っていた。当時、尾道にいた林芙美子は、祖母の通っていた
尾道市立高等女学校(現尾道東高等学校)の先輩であったのだ。
この祖母に事あるごとに連れられて行った尾道・・・このまちは私にとって
も「故郷」といってもいい。若い頃の私には、このまちは「心の砦」といっ
てもいいかも知れなかった。
夏休み、などの時には長い間預けられていた。そして、ゆったりとした時間
をこの町で過ごすことが出来た。ギラギラとした真夏の太陽は、町の景色を
私の体にも心にも焼き付けていったのだった。夏の終わり頃、父母が車で
岡山から迎えに来る・・・それまでの時間、私は尾道の子に成りきってい
た。そして、その都度、岡山へ帰ることを拒んだ。ここで暮らしたい、と。
父母は本気で、小学校の間だけ尾道の学校へ入れようか、と相談し始めて
いた。私は、そうなることを願った。しかし、岡山へ帰ると、もとの生活に
もどるのが常であった。私は後に、若しこの時それがかなっていたら、また
違う青春時代を過ごしていただろうと、何度思ったことか・・。
祖母の弟に連れて行っていただいた、耕三寺、鞆の浦、瀬戸田・・
水中翼船・・(ホバークラフト)といったと思う、海の上を走る船・・
まるで違う世界の出来事のようだった・・。翌年も、今度は父母、そして
紅風夫妻とも一緒であったと記憶している。
「けっして消えることのない何か」が、この空間にはあると感じていた。
いや、「消してはいけない何か」を感じていたのだろう・・・
紅風が嫁いでいくまで、私たちは岡山で同居していた。紅風と私の「記憶」
に残る原風景は同じものである。子どもの頃私は、私が通う小学校のすぐ
隣にあったキリスト教会の日曜学校へ通っていた。毎週の日曜日の礼拝は
その頃の私にとっての楽しみのひとつだった。もちろん家では、かなり
厳粛な「仏教徒」としての生活を日常としていた。それは極めて自然なもの
であり、堅苦しいものなどではなかった。しかし、私は教会の日曜学校へ
行っていた。これは、当時私たちが暮らしていた家の近くには二つの教会が
あり、そして、幼友達のH君がその教会に通っていたからだったか、ある
いは一緒に行き始めたのかは、少し曖昧だ・・。
その頃の私にとっては、この教会で聞くお話は、たいへん「夢のある話」で
あった。目の前には、十字架にかかった人物の姿がある。しかし、ここで聞
く話は暗さ、重々しさは感じられなかった。それよりも・・春の日差しのよ
うな柔らかさと、優しさだったろうか。女性の先生が二人おられたと記憶し
ている。
「イエスの生涯」の話を聞き、賛美歌(聖歌)を歌い、僅かばかりの献金を
して、時に・・小さくちぎられたパンと葡萄のジユースが順番に配られて
きた。私たちはそれをいただいた。そのひとつひとつが、興味深いもの
であった。「礼拝」が終わってからも、子供たちはすぐには家には帰らな
かった。その日の当番の先生と、何かしら話をしてから帰るのが常で
あった。そして、「今日のお話」について、いろいろと尋ねたりもして
いた気がする。おいくつぐらいの方だったのだろうか・・話が大変お上手
だった。今思えば、「新約聖書の福音」を子供向けに上手くまとめてお話
されていたのだが。いつもお話される先生は、鼻の横に、少し特徴のある
ホクロのある方だった。子供たちに「イエスの話」をすることが、うれしく
て仕方がない、といった気持ちが伝わってくる方だった。
いつだったか、この先生とお話しながら、私は自分が中学生になったら、
そのすぐ近くにある「大きな教会」へ行こうと思うことを告げたことがあっ
た。実はそれは何の根拠もない話だった。私は、かってに大きな勘違いを
していたのだった。いつも、こどもたちで「礼拝」をしているので、中学
になったなら、大人たちの行っているあの「大きな教会」に行くことになる
のだと、勝手に勘違いをしていたのだった。そんなことなど、あろうはずも
ないのだ。この教会はプロテスタント、そしてあちらの教会は
カトリックだったのだ。私はそんなことさえ知らなかった。
その時、その女性の先生は、急に寂しそうな、哀しそうな表情になり・・
「この教会のプロテスタントの教えは・・」と何か言いかけられた。
そのあと、しばらく、ちぐはぐな会話がなされたと思う。私が思い違いをし
ていたのだから。この方は、一人でも多くの子供にも、そして大人になって
からも、自ら信じている「イエス」を伝えていきたかったのだろう。
数十年も前の話だ・・この先生も、もちろんそんなことなど憶えてはおられ
ないだろう。しかし、私はその時のこの先生のことを、思い出す度に、申し
訳ない気持ちで胸がいっぱいになるのだ。深い信仰をもたれた、立派な方で
あったと思う・・。
その後、「洗礼の時」がやってきたのだったと思う。しかし、私は、受けれ
なかった。母親が許さなかったのだった。当然のことだったのだが・・・
私の「日曜学校」はそこで終わった。
しかし、そこでの「思い出」は数多くあるのだ・・・。
南無阿弥陀仏
